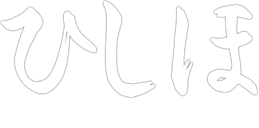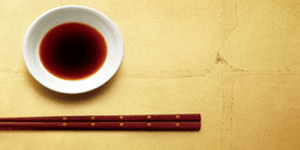馬肉生産量 全国二位の会津

春が旬と言われ、その肉の色からも「桜肉」の名がついたとされる馬肉。日本では675年から約1200年もの間、肉食が禁じられた歴史があります。しかしさまざまな地域で、馬は桜、猪はぼたん、鹿はもみじと美しい別名で親しまれ、密かに食されてきました。
現在馬肉は、低カロリー、低アレルギーで高タンパクという栄養面、また牛に替わり生食ができる肉として、注目を集めています。国内で馬肉といえばまず熊本が知られますが、近年それに次ぐ生産量を誇るのが、会津地域。会津の馬刺は、熊本でイメージされる霜降りとは全く異なる、赤身の肉だといいます。さらに純国産で生産しているというその実態を確かめに、会津若松を訪ねました。
会津の馬刺はなぜ赤い?

会津で食用馬の牧場運営から食肉加工まで一貫して行っている、株式会社会津畜産の専務取締役、宮森大典さんに話を伺いました。
「会津の馬刺が赤身なのは、品種からきています。もともと北海道で生まれ育ったサラブレッドで、軽種という品種です。レースに不向きな性質だったり、怪我等で出場できなくなった馬を引き取り、ここで食用へと肥育しています」
肉が赤身なのは、筋肉質で運動を好むサラブレッド種であるから。反対に、大型の重種といわれる馬は霜降りでサシ(細かい脂肪)が入ります。
会津畜産の畜舎では、馬に極力ストレスを与えないよう、一頭にひとマスのスペースが充てられます。飼料は大麦やトウモロコシなど穀物が中心。去勢も交配もせず、二カ所の牧場で雌雄300頭ほどを肥育しています。
会津にくる時点では、雌雄、年齢、運動や出産の経験差など、馬によってさまざま。どのくらい肥育すれば商品になるのか、一頭ごとに異なり判断が難しいといいます。
「馬は個体差が激しく、飼料の好き嫌いもあります。でも手間をかけることで、確実においしくなるのです」
東北の地で育まれた馬食文化

馬は農耕や物資運搬の要として、暮らしになくてはならないパートナーでした。肉食が禁じられた中でも、怪我や老衰などで働けなくなった馬を、人々が大切に、最後は食用としたことは想像に難くありません。残念ながら禁止令があったために、肉食に関する古い文献は残っていないそうです。
東北では、いまも広範囲にわたって馬を食べる文化があります。ただし秋田や青森では煮込み料理が多いのに対して、会津ではほとんどが馬刺。そのきっかけは力道山だった、という話も残っています。かの力道山がプロレス興行で会津を訪れた際、馬肉を生で注文し、持参していた辛子味噌を付けて食べたのだそうです。辛子味噌とは、唐辛子とすり下ろしたニンニクを混ぜ合わせたもの。現在は馬肉の販売店ごとにオリジナルの辛子味噌を作っており、会津で馬刺を食べる際には欠かせないものです。
「それ以前から生でも食べていたと思います。越後街道の峠の手前に馬の競り場と屠畜場があり、新鮮な肉が手に入りましたから」と宮森さん。そんな馬刺を女子供は食べさせてもらえなかった、と会津料理店「鶴我」の店長、山田智美さんは振り返ります。
「私は生まれも育ちも会津ですが、二十歳を過ぎるまで馬刺を食べたことがありません。秋茄子のように体を冷やすと聞いていましたが、初めて食べたときはあまりのおいしさに驚きました。父に騙されたと思いましたね(笑)」。稲刈りが終わり、豊作を祝う酒宴での男衆の最高の酒の肴が、馬刺だったのです。
昨今の牛の生食によるトラブルで、生で食べられる馬肉の需要が増えています。馬は牛よりも体温が高く、菌や寄生虫が少ないと言われています。会津畜産でも実際にユッケの注文が増えているそうです。さらなる普及のため、数年前に『会津さくらプロジェクト』を立ち上げ、地元の料理人や主婦とレシピ開発も行っています。
「会津の馬刺は赤身でやわらかく、霜降りとは味が全く違います。このおいしさを、ぜひ多くの方に知っていただきたいですね」